建築施工管理の納め方、ディティールを学ぶための書籍はたくさんあるのですが
店舗系の施工管理者が読むための書籍は皆無です
これは私が知っている知識をまとめるしかない。ちょっとした使命感でこの記事を作っています
これから店舗の施工管理として頑張る方や
先輩の方々にも共感していただけるのではないでしょうか
今回は製作図チェックについて
今回は意匠図を理解しないと製作図はただの紙切れ、価値のないものになってしまうと言うことを書いてみました
ご一読いただけると幸いです
✔︎「製作図チェック」4つのポイント
工場からの製作図をチェックするには、設計者の意図を理解しないと誤字脱字を添削するだけの作業になってしまいます。
「製作図をチェックする」というのは
- 寸法の間違いはないか
- 部材のサイズ等の間違いがないか
- 必要な強度や構造を満たしているか
- 設計者の意図を汲んだ施工をするための図面となっているか
最も重要なのが、設計者の意図を汲んだ施工をするための図面となっているか
ここを間違っていると、せっかく描いた図面は意味をなさなくなります。
もちろん寸法の間違いや、部材のサイズ等の間違い勘違いがないことも重要なポイントです。
この製作図は果たして意匠を尊重しているか、強度や構造に無理のないように製作することができて納期の期日を守れる内容か

「納期が間に合わない」と言うセリフは恐怖です…
全ての項目をクリアしているか
これをチェックすることが、『製作図チェック』となります。
初めて行うのは「ちょっと何言っているか、わかんない」状態かもしれません
一度失敗するとわかることかもしれませんが、そうも行きませんので
出来上がった姿を想像してみてください
私が新人だった頃は製図台で図面を描いていました
ペン置きからよく落ちるんです
落ちるとペン先が高確率で折れます
このペンを使用したときは衝撃でした
運悪くペン先で落ちない限り、床に落ちた衝撃でペン先が収納され
ペン先が折れる確率がグッと減りました
もう大分使っていますが、今まで折れたのは1回です
ペン先が収納されないものは運良くペン先で落下しないとしても、バウンドの時にペン先が曲がることがよくありました
✔︎設計意図のニュアンスを掴むこと
ちょっとしたニュアンスが伝わらないことってあると思います。
本当はこうしたかったのに、なぜかこうなってしまった…とか
本当はこう作らないと意匠を表現することはできない
最終のイメージを共有できているのは、意匠をイメージした設計者と私たち施工者となります。
そこへ続くのが、職人と工場製作者です。
職人と工場製作者にどれだけクオリティが高い状態で伝えられるかが肝になってきます。
設計者と施工者がどれだけイメージを共有できているか
それに尽きます

仲良し=共有できている
ではないよ!
ニュアンスとは
言葉などの微妙な意味合い。また、言外に表された話し手の意図。
ニュアンスは設計図書だけでは読み取れないものです
せっかく設計者と施工者は対面の機会が持てるのですから、打合せの機会では設計意図を共有しましょう。

ニュアンスは「空気を読む」ことと同じかもしれませんね
✔︎施工者にしかできない仕事
そして、ここからが施工者の腕の見せ所!
そのイメージを噛み砕いて、いかにわかりやすい図面に仕上げるか
- 設計意図を理解する
- それをわかりやすく伝える
【失敗例】
- 設計の意図を理解していない

「思ったのと違う!」
- 製作の段階で伝え方を間違えてしまう

「違う違う、そうじゃない…」

恐ろしや…
設計の意図を読む。なかなか難しいですが頑張りましょう!
鉛筆の上からボールペンでなぞるとカスレませんか?
ジェルインキなのでヌルヌル描ける
描いたらすぐに消しゴムで消せるのでとても重宝しています。
✔︎伝え方を間違えると起こる、ありがちな失敗例
設計意図を理解してしっかりとした形で指示を出さないと起こる失敗があります。
それは気を利かせてくれた結果の失敗です
工場はいかに効率よく作れるかを考えてくれます。
結果、勝手に素材を変更してしまい
指示したものと違うものが納品されてしまう。
工場はいい意味では無駄(ロス)のないように提案してくれる(無駄を省く)
悪く言うと、イメージを共有できていないから、ズレたものを提案してくる

ステンレスよりスチールが安いから、安い方にしといたよ!

違うもの納品されても困っちゃうな…

噛み砕いて、わかりやすく伝える
でも守らなきゃいけないことをハッキリと明確に伝えること!
色々なマジックがありますが、このplaycolorシリーズは色幅が多いので選ぶのが楽しいです
私はドス黒い赤のほうが好みなので、この「べにいろ」をよく選びます。
太さもちょうどよく、書き心地も「うぉー描いてるぞー!」
と、ちょっとテンションが高くなります
✔︎「ズレたもの」を作らせないために
なぜズレたものを提出してくるのか
それは
製作者へ渡された発注図が、イメージを共有させるための内容を満たしていない図面だからです。
【最重要ポイント】
意匠図の内容を自分に取込む
【チェック事項のキホン】
- 寸法の間違いはないか
- 部材のサイズ等の間違いがないか
- 必要な強度や構造を満たしているか
★『意匠を具現化させるために』伝える手段
まずキホン中の基本ですが、具現化させる役割の施工者が、しっかりとイメージを理解すること

↓

↓


↓

しっかりと職人さんや、工場製作者へ具現化させるために、ありとあらゆる方法を駆使して
「伝える」こと
その結果、手法として出てくるのが「製作図」「施工図」「スケッチ」です。
この図書が発注図となり、この図面をもとに現場が製作に入ります。
竣工図書に入るのは「製作図」「施工図」まで、「スケッチ」は竣工図書には入らない
まとめ:図面チェックの意図
「製作図をチェックする」というのは
- 寸法の間違いはないか
- 部材のサイズ等の間違いがないか
- 必要な強度や構造を満たしているか
- 設計者の意図を汲んだ施工をするための図面となっているか
- 設計意図を理解する
- それをわかりやすく伝える
- 意匠図の内容を自分に取込む
私の経験がみなさんの参考になればうれしいです。
建築現場が良い環境になることを願って!

・記述添削サービスを受けられる
・モギ試験がある
・出題傾向を分析したマニュアルファイルがある

・施工管理技士にオススメ
・建築士にオススメ
私のバイブルです
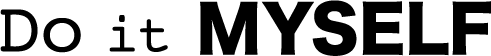


コメント