壁についているハンガーラック =wall hanger
壁についていて浮いている棚 =wall shelf
床から生えているハンガーラック =自立ハンガー
店舗内装工事をしていると、施工方法として必ず使う技術です。
こちらは私が新人の頃に教えてもらえなかった技術です
ぜひご一読いただけると、ステップアップできると思います。
まず最初に基本です
インローとは印籠のことです。
インロー = 印籠

インローは下地金物に分類されるんだ!
実際は印籠のフタ部分の構造のことを指すのですが
建築の業界では、このフタの部分の構造を印籠(インロー)と呼びます。

茶筒もインローですね!
✔︎インローを使うのはどんな時?
インローの構造は仕上げの「物」を自立させているように見せる為の見えない構造です。
仕上がると内部に納まるので見えなくなります。

縁の下の力持ち
決して表には出てこない存在…
| 使い方 | インローの構造 | |
| 壁に浮かす | → | 支えるための構造 |
| 床に固定する | → | 動かないようにピンの役目 |
目に見える形で固定金具などがついていない場合、ほぼインローの構造を使用しています。

例えば、Lアングルが付いていない棚
床から自立しているハンガーがあったとします
まず、インローと思ってください
✔︎インローの種類
インローには内に入れて見せない事もでき、逆に外に出して見せることもできます。
| 使いかた | インローのタイプ | |
| 見せないインロー | → | 内インロー |
| 見せるインロー | → | 外インロー |
内インロー


外インロー


外インローは見えるので、仕上げをする必要があります。
✔︎本実(ほんざね)と印籠(インロー)の違い
よく似ている納まりで、サネ加工があります。
サネ=実
これは床材のフローリングや、壁材の羽目板
造作の取り付け方法としてもよく使われる納め方です
調べてみると本実と印籠の構造はおなじ作りですが
両者は使い所が違うようです
印籠はしゃくり(决り)のカテゴリーに入り、本実ははぎ(矧)のカテゴリーとなります
しゃくり(决り)
建具や床板、鴨居などの造作部材を嵌めて接いだり、納めたりする溝を决り(しゃくり)という。
决りは<穿>が語源で、鑿で溝を彫り切ってつくることに由来している。决りは隙間を防ぐ役割も果たす。
はぎ(矧)
板ものを張り合わせる接(つぎ)の総称。床板や天井板、野地板など、横に張り合わせていくのに対して、板幅を縦に張っていくものを羽目板張りといい、釘を使って納めることから打をつけて目板打、相决打などど呼ぶ。
出典:図解 木造建築伝統技法事典
印籠决
「いんろうじゃくり」と読みます
縁側の一筋鴨居と鴨居、一筋鴨居と敷居を决しゃくって嵌め込み継ぐ(接)納まり。

本実矧
「ほんざねはぎ」と読みます。
床板、羽目板、天井板など比較的ていねいな矧はぎ合せで隠し打ちとする。
板ものを張り合わせる接(つぎ)の総称。とはこのことです

✔︎工程でもっとも早く準備するべき
インローは下地金物として金物屋さんが作ってくれます。
もちろん、製作寸法など細かい指示が必要になため、図面を書く必要があるのですが
工程では初期の段階でインローが必要になります。

壁下地の造成のタイミングで必要!
いち早く製作の段取りをしましょう!
できれば墨出しの時に現物が手元にあるのが望ましいです。

墨出しの時に現物を確認できると安心だよ
意外と忘れがちなので要注意です!


私の経験がみなさんの参考になればうれしいです。
建築現場が良い環境になることを願って!

・記述添削サービスを受けられる
・モギ試験がある
・出題傾向を分析したマニュアルファイルがある

・施工管理技士にオススメ
・建築士にオススメ
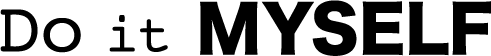




コメント