- 精度が高い図面を書くのは施工者
- デザインレベルが高い図面を書くのは設計者
- 精度が高い図面は後々重宝される
改装するときにも使えるし、なにより情報が正確であることが強み - 設計施工を請負う会社というのは、内部で設計者と施工者で部署を分けているパターン
- 両方、設計者が施工、施工者が設計を担当するパターンがある
- 設計者は設計のみに専念できれば良いが、施工の繁忙期はそうもいかず現場管理に駆り出されることもある
- 逆に施工者が設計に駆り出される事はあまりない
✔︎設計者が現場管理をするとおきる問題
設計者が現場管理をする事の最大のデメリットは、施工精度が低い事です。

設計会社だけど、最近施工も請けることにしました〜
施工精度が低いのに、なぜ施工を請けるのか
それは設計よりも施工の方が儲かると考える会社が多いからです。

実際、設計よりも施工のほうが儲かるとおもいますが、それは
利益率の差です
施工の方が利益率が高い!
施工はリスクが高いためにその対価が高いという事でもあります
引く手あまたの設計会社は、施工を請けることはリスクが高いので施工は請けようとはしません。
施工のリスクを取るよりも、設計に力を入れた方がコストバランスが良いということです
施工リスクとは
施工のリスクとは、やはりなんと言っても施工不良です。
基本的に施工不良は施工会社にあってはならないのですが、無いとは言い切れません
万が一施工不良が起きた際は責任を持って対処します。
施工会社が起こす施工不良と、設計会社が施工を請けて起こす施工不良は、大体において次元が違います。
施工会社は施工の要所要所で問題になるポイントをクリアしながら施工します。
蓄積したノウハウがあるからです
施工とは、いかに施工不良を起こさず、平然と引き渡せるか
これに尽きると思います。
施工不良が起きてしまった時、施工会社に対する顧客の信用度が落ちてしまいます。
信頼の回復方法は、施工不良をどれくらいの完成率で修繕できるか、その対応で顧客の信用を回復できるかが決まります。
設計会社と施主の信頼関係
設計会社にとって施主との信頼関係が最も大事なことです

信頼関係があった上で設計を頼むわけですからね
形のない状態からデザインを信用して任せてもらう
出来上がったものが顧客のイメージ通りに出来上がると信頼度はさらに向上し、次の物件につながる可能性もあるでしょう
また、信用できる設計会社として評判となり依頼が集まる可能性があります。
この様に、設計会社にとって施主との信用はとても大事なモノなのです
この信用が崩壊する時、設計会社にとって致命傷となり存続の危機なんて事なることも
施工不良を是正するためにはとてつもない労力と時間が必要です。
何もないところから作るほうが良いこともあるほどです

ごく稀に、一度解体して作り替えることがあります
施工者はとことん是正に向き合います、対して設計者は施工者ほど真摯に向き合わないと言って良いでしょう
向き合わないと言うよりも、向き合っている時間がない
設計者はやはりデザインが本業なので、いつまでもその物件の是正工事で人員をとられているわけにはいかない
と言うのが本音です。

いつまでかかっているんだ?
早く本業に戻ってくれよ

ひどい話ですがホントにあることです
引く手あまたの設計会社ならば、信用を失う可能性が高い施工は請けようとはしない
なぜなら施工を請けるリスクは、施工不良が起きた時その物件に時間を取られてしまうため、採算が合わない事
設計会社が施工をすることのメリット
設計会社が施工を請けると儲かるのか
答えは、儲けようと思えば儲かる。です
- 心を鬼にすること
- 顧客をいかに信用させることができるか
この2点に尽きます。
これができれば設計会社が施工を請けて儲けることが出来ます。

施主側としては賭けである
儲ける方法
設計者が施工を請けて儲けるためには、心を鬼にすること

良心を捨てるのです
具体的に何をするのか
設計会社が不慣れな施工を請けるため失敗が多くなります。
発注ミス、製作管理のミス、仕上げの失敗など現場でミスが起こる
どうする?
発注ミスは、そもそも無かったものとする。
ミスがあったデザインは無かったものとする、設計段階からなかったとするんです。

元々無いんだから、現場にもないよ
ある訳がないよ。としちゃうんです
施主に、なんで無いんですか?と聞かれても
「計画でなくしました、こちらの方が断然いいですよ」

なんで無いんですか?あったと思うけど

無いほうが全然イイですよ!

まぁそう言うんだったら、そうかも知れないね
施主との信頼関係があればこれを通すことができます

『納品したらぜんぜん違う!』
仕方ない、これが正解なんだ!これが欲しかった!
と、思うことにしよう
もうやりたい放題です…
施主との信頼関係の上で、この裏切り行為は起こっているんです。

こうやって設計施工で儲けているんだね
失敗や不具合を無かったものにするとナゼ儲かるのか
その仕組みは簡単で、通常、施工会社の施工で不備が有った場合、施工者の責任で是正工事を行います。費用は施工会社が負担します。
施工会社の失敗なので、自分の利益が減ることになります。
設計会社が施工を請けて、ミスが無かったことにしてしまった場合
是正工事にかかる費用が必要なくなり元の利益が守られます。
ミスを無かったことにすることで、儲けを生むんです

これはバレたら信頼関係は崩れますね
※これは私の経験です。このような背信行為を行わない設計施工会社はたくさんあります。ご了承ください
私がいた会社では、引渡し時にこちらの都合の良いように、上司が話をしていました。
話術ですね
私としては、私が犯した失敗を上司がフォローしてくれた。と考えていましたが
次第に「あれ?施主が頭をかしげているぞ?」何かがおかしいと気づき始めました。
何せ社会経験もないため「社会ってこんな感じなんだぁ」くらいに思っていました。

今考えるとオソロシイ
✔︎施工会社が設計を請けると
もちろん施工者が設計を行うこともある
そのメリットは、精度が高くて現実味がある設計図となる事
デメリットは、施工の限界がわかっているから攻めたデザインができなくなる

つまらないデザインってことですね
施工会社の本音
施工会社の強みは建築コストを管理する事に長けている事
その強みを活かして、施主の希望と施工コストをコントロールしつつ設計を行いたい!
しかし、攻めたデザインが出来ないので設計を請けることが出来ない
なんとかならんかー
✔︎設計施工会社として成立させるために
設計施工会社として成立させるためには、社内で設計部署と施工部署を明確に分けることです
設計はデザインに専念する!
施工は施工に専念する!
ごく当たり前のことですがそれが出来ないんです
それは、会社内の収支がパワーバランスに影響しているからです
会社の収益の大半を占めるのは、やはり施工なので設計に対して意見を言えるわけです
仮に設計が攻めたデザインを計画していても、施工性が悪く収支が悪いので設計変更を要求する
なんて事もあります。

費用対効果が悪い
とかです
そうなると必然と施工性の良いデザインになり、デザイン性が疎かになってしまう。
このデザイン性をしっかりと設計部署を守ることができる施工会社は強いです

デザインも素晴らしく、施工も精度が高い
サイコー!
大手施工会社の手法は「設計を囲う」やり方です。
タブーの話ですが、物件(施主)をたくさん流す=こっちの言うこと聞いてね!(やりやすいように)
件数があれば売れっ子の仲間入りとなり、著名な先生となります。
著名な先生もこのやり方で有名になっています。
まとめ
設計者は施主の信頼を受けてデザインと設計を行っているため、不都合な箇所はごまかすことができる
これがしたかった事なんだ。と言い切ってしまえば良い
利益を得るために都合のいいように仕上げ変更を行う
これがしたかった事なんだ。と言い切ってしまえば良い
このことを理解してお付き合いをしてみましょう。
設計会社が最近施工も請けるようになった
そんな時は気をつけてください
※これは私の経験です。このような背信行為を行わない設計施工会社はたくさんあります。ご了承ください
私の経験がみなさんの参考になればうれしいです。
建築現場が良い環境になることを願って!




・記述添削サービスを受けられる
・モギ試験がある
・出題傾向を分析したマニュアルファイルがある

・施工管理技士にオススメ
・建築士にオススメ
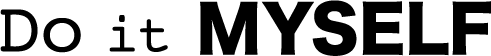

コメント