建築施工管理の納め方、ディティールを学ぶための書籍はたくさんあるのですが
店舗系の施工管理者用の書籍は皆無です
これは私が知っている知識をまとめるしかない。ちょっとした使命感でこの記事をつくりました
これから店舗の施工管理として頑張る方
先輩の方々にも共感していただけるのではないでしょうか
今回は建具を枠とフラットに納めることについてです。
ご一読いただけると幸いです
詳細図(平断面、納まり案、鴨居断面)

特にアトリエ系、先生事務所と呼ばれる設計会社から、出てくる図面に多くみられる書き方です。
一見とてもシンプルで「あ、簡単な建具ね」と思ってしまいそうな図面ですが
これはトラップです
実際製作に入ると、とても大変で手間も掛かり大変苦労します。

気をつけて!
「フラット納まり」にする設計者が、考えていること
設計者はこんなふうに考えています
- この絵を見たら施工者ならわかるだろう
- 特に納まりが〜など考えておらず、とにかく壁をフラットにしたい(金額見てビックリ)
- 予算が合わなかったら普通の納まりに変えるつもり、とりあえず予算取り
確かにフラットにするとシンプルでスッキリ見えるのですが、作り手としてはかなり高度な技術力が必要です。
建具枠と建具(ドア)をフラットにしたい

とてもシンプルな絵です。
しかし、この建具を作るためにはたくさんの項目がありますので
チェックしてみましょう
設計の意図として、壁と枠は「フラットに納めたい」と思っているのでしょうから
枠も壁とフラットにするのがベストだと思います。
- ポイント:製作に手間がかかるのでコストアップします
- リスク:ドアの開閉時に振動が常に発生するので、クラックが入る
ほぼ確実にクラックが入ることを承認してもらう(奇跡的にクラックが入らないこともある)

クラックは必ず入ります!
1.戸当たりの検討
ポイント!
そもそも、なぜ相欠きなのか
戸当たりであれば扉の上部にあるだけでも機能します。
ではなぜ縦方向の相欠きにする必要があるのか、
それは『反り』が発生するためです
板にしたものは必ずと言って良いほど『反り』が発生します。

木材、金属関係なく反ります
木材はみなさんが想像するように、反りやすいです。
金物の板材の折り曲げでドアを作った場合、やはり反ります。

金属なのにナゼ反るのか、それは溶接時に熱による膨張のためです。
結論どの素材で作ったとしてもドアは反る
上部の鴨居だけでは、反りが発生した分の「狂い」を吸収することはできません
縦枠を戸当たりにすることで、反りによって生じた狂いを吸収することができるのです。

帳尻を合わせるんです
扉を枠とフラットに納めるためには、縦方向の相欠きを基本として考えた方が、納まりが良いと思います。
1-①.相欠き

→戸先の切り欠き

→片方の縦枠と上部の鴨居は切り欠き不要
1-②.金物

→もしくは特注で作る
戸先の相下記の代わりにフラットバーで対応することができます。
この方法だと相欠きの加工費用を抑える事ができますが、内側から見た時の印象をどう考えるかです。

相欠きだとスッキリしていますが、フラットバーだと「ん?なんだ?」となります

両側ともスッキリ見せたいナ
見た目よりもコストを優先させるならフラットバーをつけるのもアリです。
例)バックヤード、ストックルームなど
2.ドアを閉めるための手段・方法
2-①.ドアクローザー スタンダード型

→メイン側には見せたくない時
ドアサイズが900×2100とありますが、ここら辺の近似値として考えてください
私は800×2000でも7002の品番を選びます。
重量は45kgとなっていますが、私はここから1割程度を軽くして考えています。

軽すぎても機能の持ち腐れになるためです

→ドアクローザーの枠側は特殊な形状になる
ニュースターでは、天井までのアームの取付けに必要な寸法が確保できない時のため、H型アームを選定できます。
ただし、ストップ機能はつける事ができません
2-②.ドアクローザー コンシールドタイプ
メリット→両側(部屋内、外)ともにドアクローザーを見せたくない
デメリット→コストアップ、納まりが難しい
2-③.オートヒンジ

→丁番本体が大きくなる

→吊元には高負荷が掛かるので、強度を検討する必要がある
→経験則では使用頻度が高い場所には不向き
2-④.フロアヒンジ
→床に埋めなければならないので、躯体条件による
⇨埋設深さを確保できるか
⇨アンカー固定ができるか
両方ともクリアしていないとフロアヒンジは選定できません

フロアヒンジをビス止めする事がありますが強度は担保できません
ビスが折れます
2-⑤.手動
扉の開け閉めは自らの手で行い
閉まった状態を保持するために、ラッチを使用します。
ラッチの取付方法を要検討

3.ラッチを付ける事ができるか(ストライクの彫込み)
3-①.三角ゴンベ

建具で使用する「マグネットローラー締り」や「三角ゴンベ」は(大)を選定してください
(大)くらいの大きさがないと建具の重量を受けきれません

中や小では建具をグッと掴みきれないんです
ドアが開いちゃう〜 って事です
3-②.ケースロック(レバーハンドル)❌

レバーハンドルを使う方法も考えられますが、この場合、表側にハンドルを付けない為ラッチを回す事ができず、開けることができません
よって、レバーハンドルは使えません
4.錠前をつける事ができるか

【LAMP(スガツネ)】面付シリンダー錠 A-627型
建具に鍵をつけるための選定条件
- 戸厚
家具用の面付けシリンダーの首部分の長さは大体が22mmです。これは引出しの正面板(妻板)の寸法により依存しているためです。
今回はドアの厚みが30mmとして、シリンダー首の長さが30mm以上あるものを条件として選びました - 戸先が相欠きなので鍵の引っかかりのベロ部分(出入りする箇所)が長い物を条件としました。
5.壁と枠の納まり
壁と枠の納まりは、別の記事で色々と書きましたので併せて読んでいただくと
「なるほどね」
と思っていただけると思います。
枠周りはほぼ間違いなくクラックが入ります
異素材で見切る、隠す等のテクニックが必要です。
しっかりと対策をとってください、クレームの対象となるのは間違いありません


まとめ
今回出した納まり案は私が実際に行って納めたものと、予算の関係で実際の施工には繋がらなかったものです。
これらの納まりは一つの例であり、この例をベースに新たな納まりとすることができます。
考え方の一つとして参考にしていただければ幸いです。
私の経験がみなさんの参考になればうれしいです。
建築現場が良い環境になることを願って!

・記述添削サービスを受けられる
・モギ試験がある
・出題傾向を分析したマニュアルファイルがある

・施工管理技士にオススメ
・建築士にオススメ
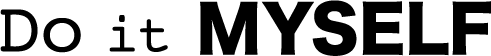



コメント